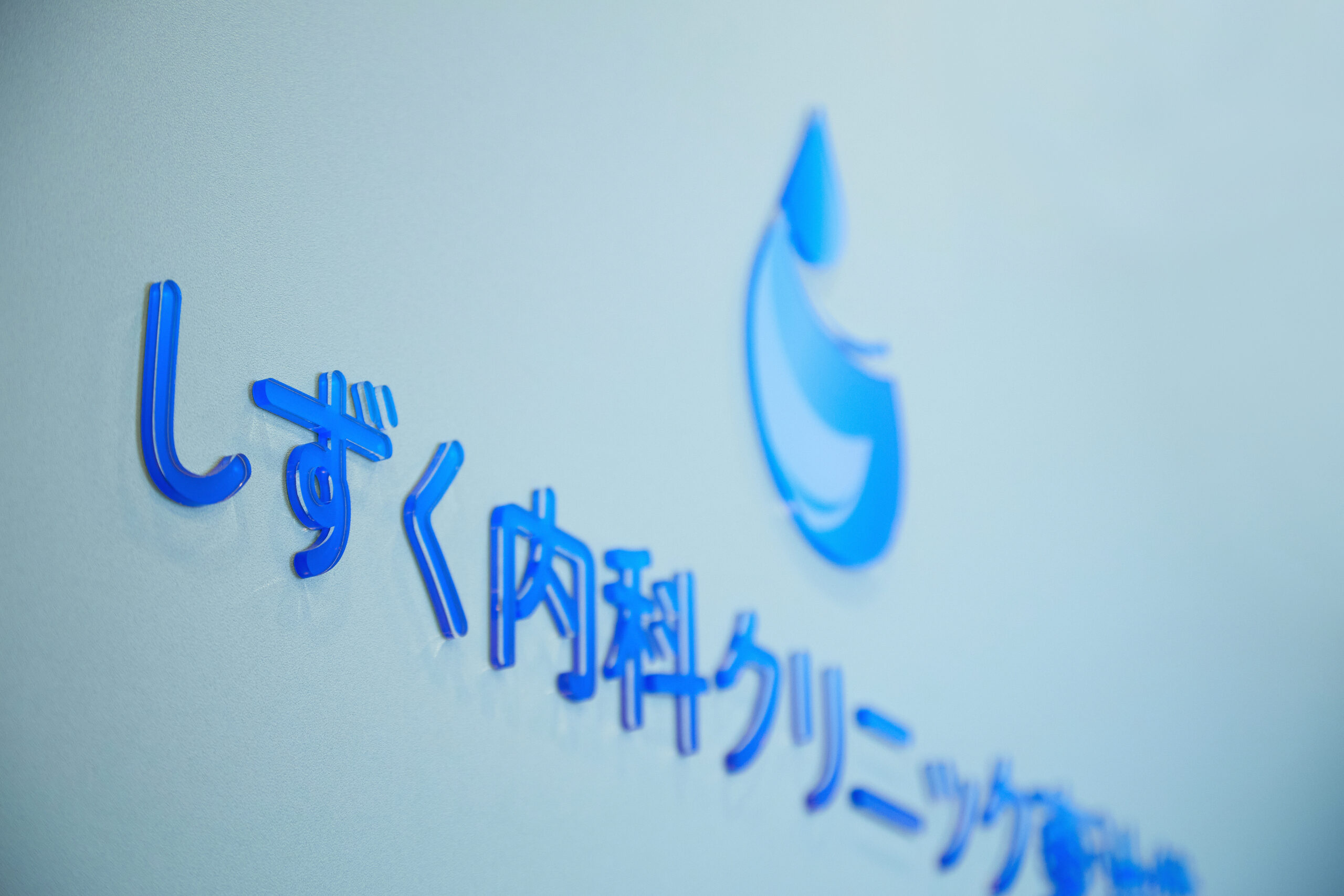梅毒とは
梅毒は、梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)というらせん状の細菌が引き起こす代表的な性感染症です。主に感染者との性的接触(性行為やそれに類する行為)によって、相手の粘膜や皮膚から細菌が体内に入り感染します。感染から一定期間後に全身のさまざまな部位に症状が現れることが特徴で、放置すると皮膚に赤い発疹(※楊梅〔ヤマモモ〕の果実に似ていることから「梅毒」の名がついたと言われます)が出たり、長い経過ののちに脳や心臓などに重大な合併症を引き起こすこともあります。
しかしながら、現在では適切な抗生物質による早期治療で完治可能な病気です。大切なのは、症状が良くなっても自己判断で治療を中断せず最後まで薬を飲み切ることです。不十分な治療では菌が体内に残り病状が進行してしまう恐れがあります。また、一度梅毒にかかったあと治療で治っても免疫はつかないため、再び感染する可能性があります。予防策の継続とパートナーの治療が重要になります。
梅毒はかつてペニシリンが発見される以前には不治の病と恐れられましたが、抗生物質治療の普及によって一時は患者数が激減しました。ところが近年になって感染者が再び急増しており、日本では2010年代から梅毒の報告数が増加に転じ、2022年以降は年間1万件を超える流行が続いています。
2023年の梅毒報告数は約14,900人(男性9,600人・女性5,300人)にのぼり、これは届け出制度開始以来最多となりました。特に20〜50代の男性および20代女性での感染拡大が顕著で、若年層への広がりが懸念されています。増加の背景には、若者の性感染症に関する知識不足や、SNS・マッチングアプリを介した出会いの増加による不特定多数との性的接触機会の増加などが指摘されています。梅毒は誰でも感染し得る身近な感染症として、正しい知識と予防策を身につけることが大切です。
妊娠中に梅毒に感染
妊娠中に梅毒に感染すると胎盤を通じて赤ちゃんにも感染する危険があります。梅毒感染した妊婦では流産や死産のリスクが高まるほか、赤ちゃんが感染を持った状態で生まれる先天梅毒の原因にもなります。妊娠中の梅毒感染は胎児の発育に深刻な影響を与える恐れがありますが、妊婦健診時の梅毒検査や早期治療によって母子感染のリスクを大幅に下げることが可能です。妊娠を予定している方や妊娠中の方は特に注意し、検査を受けるようにしましょう。
感染経路と予防方法
梅毒は主に性的接触によって感染します。具体的には、感染者の皮膚や粘膜の梅毒病変(梅毒のしこりや潰瘍)に触れることで菌がうつります。通常の膣性交(男女間の性行為)はもちろん、オーラルセックス(口腔性交)や肛門性交(アナルセックス)でも粘膜同士が接触すれば感染のリスクがあります。
場合によってはキスであっても、口の中に梅毒の病変があると感染しうるため注意が必要です。梅毒菌は非常に感染力が強く、ほんの小さな傷からでも体内に侵入します。ただし日常生活の中で普通に握手をしたり食事を共にした程度では感染しません。
タオルや食器の共有、入浴など日常接触でうつることはないので過度に心配する必要はありません。感染経路は主に性的接触ですが、もう一つ重要なのが母子感染です。梅毒に感染した母親から胎児へ胎盤経由で菌が移行し、赤ちゃんが先天梅毒にかかってしまうことがあります(先天梅毒については前述の通り)。
現在、日本では妊婦健診で梅毒検査が原則実施されており、陽性であれば出産前に治療することで赤ちゃんへの感染予防に努めています。
梅毒から身を守るには、不特定多数との性的接触をなるべく避け、コンドームを正しく使用することが基本です。コンドームは性行為時の粘膜同士の直接接触を防ぐ有効な手段ですが、コンドームで覆われない部分に梅毒の病変があれば感染する可能性があるため、コンドームで100%防げるわけではありません。
オーラルセックスの場合も同様です。したがって、相手や自分の皮膚・粘膜に異常(しこり・潰瘍・発疹など)を認める場合は性的接触を控え、早めに医療機関を受診して相談することが大切です。特に梅毒は第1期・第2期の感染初期が最も感染力が高いので、この時期の患者との性的接触は避けましょう。
梅毒予防のポイント
- 正しいコンドーム使用
- 性交時は毎回コンドームを着用し、根元からきちんと装着しましょう。粘膜接触のリスクを減らす基本的な予防策です。ただし完全に防げるわけではない点を心得ておきます。
- 不特定多数との性行為を控える
- 出会い系アプリなどで知り合った初めての相手とは特に慎重になりましょう。信頼関係のない複数の相手との性的接触は感染リスクを高めます。
- 定期的な検査
- 性的パートナーが変わったり複数いる場合、自分自身とパートナーで定期的に性感染症の検査を受けましょう。早期に感染を発見し治療すれば重症化や他者への感染拡大を防げます。
- 症状がある場合は性交渉を中止
- 性器や口の中にしこり・潰瘍、全身の原因不明の発疹など、梅毒が疑われる症状が出た場合はセックスをせず、すみやかに医療機関で検査しましょう。症状が消えても自己判断せず、完治確認までは性的接触を控えます。
- パートナーと一緒に治療
- 梅毒と診断された場合、自分だけでなくパートナーも検査を受けさせ、陽性なら同時に治療を開始することが重要です。どちらか一方だけ治療すると、あとで再感染してしまう恐れがあります。
- 妊婦は早めの検査
- 妊娠中または妊娠の可能性がある人は必ず梅毒検査を受けましょう。先天梅毒を防ぐために、妊婦健診でのスクリーニングと早期治療が非常に重要です。
以上の点を心がければ梅毒の感染リスクは大きく下げることができます。梅毒に限らず「予防に勝る治療なし」です。正しい知識と用心で、ご自身と大切な人を梅毒から守りましょう。
梅毒の症状と進行段階(第1期〜第4期)
梅毒では感染後、症状の出方に応じて第1期から第4期までの段階に分類されます。各段階で症状の現れ方が異なり、治療せずに放置すると段階的に症状が進行していきます。以下に、治療を行わなかった場合に典型的にみられる症状の経過を第1期から順に解説します(※症状の現れ方には個人差があります)。ご自身に思い当たる症状がある場合、たとえ症状が一時的に消失しても油断せず、早めに医師の診察を受けるようにしましょう。
第1期(感染後3週間~3ヶ月)
感染から数週間後(平均3週間ほど)に最初の症状が現れます。梅毒トレポネーマが侵入した部位に、小さなしこりや潰瘍(かいよう)ができるのが典型です。この病変は「硬性下疳(こうせいげかん)」と呼ばれ、性器(男性では陰茎や亀頭、女性では膣や外陰部)、肛門周辺、あるいはオーラルセックスによる感染なら口唇や口腔内などに生じます。しこりは米粒大から指先大程度の固い腫瘤で、中心がただれて潰瘍状になることもあります。
特徴的なのは痛みやかゆみがほとんどないことです。そのため「ニキビのようなできものかな?」と見過ごされたり、痛みが無いため深刻に捉えず放置されてしまうケースが少なくありません。加えて、近くのリンパ節(性器の場合は鼠径〔そけい〕部のリンパ節)が腫れることもあります。リンパ節の腫れも痛みを伴わず硬い腫瘤として触知されます。
第1期の症状である硬性下疳やリンパ節腫脹は、治療をしなくても約1〜2ヶ月ほどで自然に消えてしまうことがあります。実際、多くの場合は感染から1ヶ月前後でしこりが跡形もなく引いてしまいます。しかしこれは「治った」ことを意味しません。症状が消えている間も梅毒菌は体内で静かに増殖を続けており、適切な治療をしない限り次の段階へ進行してしまうのです。第1期梅毒は症状が軽度なため見逃されやすいですが、この段階で発見・治療できれば比較的短期間で完治させることができます。性行為後に原因不明のしこりや潰瘍が性器・口腔などにできた場合、痛みがなくても梅毒を念頭に早めに医療機関を受診しましょう。
第2期(感染後3ヶ月~2年程度)
初期症状が消えた後、感染から3ヶ月後くらい経過した時期から第2期梅毒が始まります。梅毒菌が血液を介して全身に広がり、皮膚や粘膜、臓器に様々な症状を引き起こす段階です。第2期の代表的な症状は梅毒性の発疹です。特徴的なのは手のひらや足の裏に出る発疹で、薄いバラ色を呈することから「バラ疹(薔薇疹)」と呼ばれます。
バラ疹は大小の赤い斑点が散在するように現れますが、痛みやかゆみがないのが普通です。発疹の色味はピンク〜赤褐色で、全身(体幹部や四肢など)にも広がることがあります。また第2期では、扁平コンジローマと呼ばれる症状が出ることもあります。扁平コンジローマは肛門や陰部、口の中などの湿った粘膜部分にできる扁平なイボ状の病変で、梅毒性のイボですがヒト乳頭腫ウイルス(尖圭コンジローマ)によるイボとは異なります。
その他、全身のリンパ節腫れ、軽い発熱、倦怠感、食欲低下、脱毛(髪の毛がまだらに抜ける梅毒性脱毛)など、多彩な症状が現れることがあります。症状の出方には個人差が大きく、一見するとアレルギーや他の疾患と区別がつかないこともあります。
第2期の諸症状も、発疹にせよイボにせよ数週間から数ヶ月で自然に消える場合が多いです。しかし繰り返しになりますが、症状が消失しても感染自体が治ったわけではありません。梅毒は「沈黙の進行」とも呼ばれ、一旦消えた症状がしばらくしてまた出現したり(再発)、症状がないまま潜伏期間に入って病気だけが進むことがあります。そのため、第2期の段階で梅毒だと気づかず治療しないでいると、本人も知らないうちに感染が全身へ広がり、次の潜伏期・晩期へ移行してしまうのです。発疹など一見梅毒と分かりにくい症状もありますので、「おかしいな」と思ったら専門医による的確な診断を受けることが重要です。
第3期(感染後2年~10年)
梅毒の症状が一旦消え、無症状の潜伏期間が長く続いた後、数年を経てから現れるのが第3期(いわゆる潜伏梅毒〜晩期梅毒の時期)です。感染から約3~10年ほど経過すると、ごく一部の未治療患者でゴム腫と呼ばれる腫瘤(こぶ)が現れることがあります。ゴム腫とはその名の通りゴムのような弾力をもった軟らかい腫瘍で、皮膚や筋肉、骨、肝臓、腎臓など全身のさまざまな臓器に生じて周囲の組織を破壊します。
また、皮膚や骨に硬いしこりができて潰瘍化するような症状も報告されています。これら第3期の症状は晩期顕性梅毒とも呼ばれ、現在では抗生物質治療の普及によりかなり稀なケースとなりました。
多くの患者さんは第2期までに診断・治療されますが、治療機会を逃して何年も経過した場合にごく稀に第3期の症状を見ることがあります。第3期梅毒まで進行すると、皮膚のただれや骨の変形などが起こり、治療してもそれまでに生じた器質的な障害が完全には元に戻らない場合があります。現在の日本ではめったに見られない段階とはいえ、治療せず放置するとここまで進行しうる病気であることは念頭に置いておきましょう。
第4期(感染後10年以上)
感染から10年以上が経過し、さらに時間が経つと第4期(梅毒の末期)と呼ばれる状態になります。梅毒菌によって心臓血管系や中枢神経系が侵される深刻な段階です。具体的には、梅毒性の大動脈炎が起こり大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう)の形成や大動脈弁の損傷につながり、最悪の場合心不全や大動脈破裂を引き起こします。
また中枢神経が侵されると神経梅毒と呼ばれる状態になり、脳や脊髄への感染によって進行麻痺(まひ)(人格変化や認知機能低下などの精神神経症状)や脊髄癆(せきずいろう)(脊髄後根が障害され歩行障害や排尿障害、深部感覚の異常が生じる)の症状を呈します。
この段階になると日常生活が困難になる重篤な症状が現れ、放置すれば死に至ることもあります。幸い現在の日本で第4期まで進行するケースは極めて稀です。梅毒がここまで悪化する前にほとんどの患者さんは治療を受けており、第4期の症状を見ることは滅多にありません。
ただし注意すべきは、神経梅毒(中枢神経への感染)は梅毒の病期に関係なく起こりうるという点です。たとえ早期の段階でも梅毒菌が脳に達すると神経症状が出現する可能性があります。そのため、少しでも「おかしい」と思う症状があれば病期にかかわらず早めに医療機関を受診しましょう
梅毒は、初期には痛みのないしこりや発疹など一見軽微な症状から始まりますが、治療しない限り数年〜十数年の経過で致命的な合併症に至る可能性がある怖い病気です。幸い現在では有効な治療薬があり早期治療で完治が期待できるため、症状が無くても感染の心当たりがある場合は迷わず検査を受けることが重要です。とくに第1期・第2期の梅毒は症状が一時的に消失するため見逃されやすく、「知らないうちに第3期以降へ進行していた」という例もあります。梅毒が疑われる症状(性器・口・肛門のしこりや潰瘍、原因不明の発疹など)に気付いたら、一人で悩まず早めに専門の医師に相談しましょう。
検査のタイミング
梅毒の感染が心配な場合、「いつ検査を受ければよいか」は悩ましいポイントです。梅毒抗体は感染直後にはまだ体内で産生されておらず、検査で陽性反応が出るまでにおおよそ3〜4週間かかるとされています。
したがって、たとえば「数日前に避妊せず性行為をしてしまった」「パートナーが最近梅毒と診断された」というケースでは、行為直後に検査しても正確な結果が得られない可能性があります。
感染の可能性がある行為からまだ日が浅い場合は、症状の有無にかかわらずまず医療機関を受診し、経緯を相談してください。医師が必要と判断すればすぐに検査を行いますし、結果が陰性でも一定期間後に再検査するスケジュールを立てる場合があります。
特に症状が無くともパートナーが梅毒と診断された場合などは、早めに受診して指示を仰ぐことが大切です。症状が出ている場合はもちろんただちに検査・治療を受けるべきですし、症状が無い場合も自己判断で放置せず専門家に相談しましょう。
検査結果の見方
梅毒の血液検査結果は、通常「陽性/陰性」あるいは数値(抗体価)で報告されます。陽性であった場合は医師が現在の感染状況(活動性が高いかどうか、治療が必要な状態かどうか)を判断し、適切な治療方針を説明します。
また梅毒以外の疾患の可能性が否定できない場合には、追加の検査が行われることもあります。陰性であっても、感染の可能性がある行為から間もない場合は念のため一定期間後に再検査するよう勧められることがあります。検査結果について不明な点があれば遠慮なく担当医に質問しましょう。
よくある質問(梅毒の検査Q&A)
治療法と注意点
梅毒の治療は抗生物質の投与によって行います。梅毒菌はペニシリン系抗生物質に非常に感受性が高いため、現在でもペニシリン系抗菌薬が第一選択です。具体的には、かつては日本では主に経口(のみぐすり)の抗生物質を1日数回服用する治療が一般的でした。例えばアモキシシリンなどのペニシリン系内服薬を、梅毒の期別に応じて2〜4週間程度服用します。2021年9月には、日本でも梅毒の標準的治療薬である長時間作用型ペニシリン注射剤(ベンザチンペニシリン筋注剤)が承認されました。
この筋肉注射製剤は1回の注射で血中薬剤濃度が長期間維持できるため、欧米では梅毒治療の第一選択となっています。日本でも今後、ベンザチンペニシリン筋注による治療が広がる可能性がありますが、現時点では医療機関によって対応が異なるため、主治医の判断に従ってください。いずれにせよ、梅毒は適切な抗生物質治療で完治が期待できる感染症ですので、陽性と診断されたら速やかに治療を開始しましょう。
治療は外来通院で可能です。内服治療の場合は処方された期間しっかり薬を飲み続け、医師から「治癒」と確認されるまでは自己判断で中断しないことが肝心です。症状が治まっても菌が完全に死滅していなければ再増殖し得ますので、処方された薬は最後まで飲み切ってください。また、治療開始後しばらくは性交渉など感染を広げる行為は控えるようにしましょう。治療によって血液中の梅毒菌は減っていきますが、治りかけの時期でも油断せず、医師から性的接触再開の許可が出るまではパートナーとの接触を避けてください。パートナーにも検査・治療を受けてもらい、お互い完治するまでは性行為を控えることが再感染予防のために重要です。
- 副作用やアレルギー症状に注意してください。ペニシリンアレルギーのある方には別の系統の抗生物質(テトラサイクリン系など)が用いられます。内服薬で胃腸の不調など軽い副作用が出る場合もありますが、多くは一時的なものです。我慢できない副作用が出た場合はすぐ医師に相談しましょう。
- 治療開始から数時間以内に発熱や倦怠感、発疹の悪化が見られることがあります。これはヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応といって、抗生物質で大量に殺された梅毒菌から放出される毒素による一過性の反応です。梅毒治療ではしばしば起こる現象で、通常は1日〜2日で収まりますが、症状が強い場合は対症療法を行います。焦らず主治医の指示に従ってください。
- 治療後の経過観察も重要です。梅毒治療が完了した後も、一定期間は血液検査で抗体価の低下を確認するフォローアップが行われます。治療によって非梅毒トレポネーマ検査(RPR法)の抗体価が徐々に低下し陰性化または低力価になることを確認できれば治癒と判断されます。医師から治癒の太鼓判をもらうまでは、途中で通院をやめないようにしましょう。
治療後も再感染に注意してください。梅毒に一度かかったことがある人でも、その後の生活で再び梅毒菌に接触すれば再度感染してしまいます。治療によって体内の梅毒菌は排除できますが、梅毒に対する免疫は一生得られるわけではありません。せっかく治っても油断するとまた感染する可能性がありますので、予防策(コンドームの使用やパートナーの治療など)は今後もしっかり継続しましょう。
梅毒の流行状況と患者の傾向
日本では梅毒の患者数が近年急激に増加しています。感染症法に基づく梅毒の届出数は、1948年から統計があり、1960年代までは年間数千〜1万人以上の報告がありました。その後、ペニシリン普及などにより減少し、長らく年間数百件程度で推移していたものが、2011年頃から再び増加傾向となりました。
特に2015年以降増加に拍車がかかり、2017年には約5,820件(44年ぶりに5,000件超)との速報値が報告されています。その後も上昇は続き、2019年~2020年は一時減少したものの(新型コロナ禍で受診控えがあった可能性があります)、2021年以降に再び大きく増加し、2022年はついに年間1万3千件超と過去50年以上で最多の報告数となりました。2023年も約15,000件に達し、戦後の統計史上でも類を見ない流行となっています。この梅毒流行の拡大は社会的にも大きな話題となっており、厚生労働省や専門学会は若年層への注意喚起や検査体制の強化などの対策に乗り出しています。
日本国内で梅毒患者が急増している地域としては、東京や大阪などの大都市圏が挙げられます。実際に報告数は東京都が突出して多く、大阪府・愛知県・福岡県など人口の多い都市部で感染者が多い傾向です。また、患者の年齢層・性別の傾向にも特徴があります。
近年のデータでは、男性は20代〜50代にかけて幅広い年齢層で患者が報告され、女性は20代が突出して多いことが分かっています。2010年代半ばまでは男性患者(特に男性間の性的接触による感染)が多くを占めていましたが、近年は異性間の感染による若年女性患者の増加が顕著で、男女比が縮まってきています。
その結果、梅毒感染に気付かないまま妊娠に至るケースも増え、妊娠中の梅毒感染報告数や先天梅毒の件数も2019年以前と比べ大幅に増加しています。これは非常に憂慮すべき事態であり、産婦人科領域でも妊婦健診での梅毒検査徹底や妊娠中の再検査実施など、母子感染予防の取り組みが強化されています。
梅毒流行の背景について、専門家からは性行動の多様化や避妊具不使用によるリスクの増大が指摘されています。SNSやマッチングアプリの普及で性的パートナーを得やすくなったこと、風俗産業の利用者・従事者双方で梅毒感染が広がっていること、若年層の性感染症に対する知識や危機感の不足などが複合的に影響していると考えられます。
また、新型コロナウイルス流行下でHIVや梅毒など性感染症の検査機会が減ったことが、感染の見逃しにつながった可能性もあります。いずれにせよ、梅毒の流行拡大を食い止めるには一人ひとりが正しい知識を持ち、早期検査・治療と予防策の徹底を図ることが不可欠です。
梅毒患者さまの傾向として、「自分は大丈夫」と思い込んで受診が遅れるケースがしばしば見られます。梅毒の初期症状(しこりや発疹)は痛みがないため深刻に受け止められず、「いつの間にか治っていたから放っておいた」という声も聞かれます。
しかし前述の通り、症状の自然消退は治癒ではなく単なる一時的な潜伏に過ぎません。症状が軽快しても梅毒菌は体内に残り静かに進行します。その間に知らず知らず他者に感染させてしまう恐れもあります。特に梅毒はHIV(エイズ)など他の性感染症と同時感染している場合もあり、梅毒の潰瘍がHIV感染のリスクを高めることも報告されています。梅毒の患者さまの中には「他の性病も検査してほしい」という希望を持つ方も多く、実際にクラミジアや淋病などの同時感染が判明することもあります。一度梅毒と診断されたら、他の性感染症についても包括的に検査を受けておくと安心です。
また、「梅毒は昔の病気」「自分の周囲では流行していない」と思っている方も注意が必要です。上述のように梅毒は今まさに若い世代を含めて広がっており、決して過去の病気ではありません。男性同士の病気と思われがちですが、現在では女性の患者も増えているため、性別に関係なくリスクがあります。性的接触のある人であれば誰でも感染しうる身近な感染症です。
少しでも「あれ?」と思う症状や心当たりがあれば、恥ずかしがらずに検査を受けましょう。近年の流行状況を踏まえ、厚生労働省も「梅毒を疑ったら早めに受診を」と呼びかけています。
当院での対応
梅毒かな?と不安を感じたら、しずく内科クリニック東池袋にぜひご相談ください。当院では梅毒を含む性感染症に迅速かつ丁寧に対応いたします。
- 感染症専門医による安心の診療
- 当院では、梅毒を含む感染症診療の豊富な経験を持つ感染症専門医が診察いたします。症状の現れ方や経過は人それぞれですので、専門医がしっかりとお話を伺い、必要な検査・治療をご提案します。「この症状は梅毒か分からない」といった段階でも、お気軽に受診ください。患者様の不安に寄り添い、プライバシーに配慮しながら納得いただけるまで丁寧に説明を行います。梅毒以外の性感染症検査や総合的なヘルスケアについてもご相談いただけます。
- アクセスの良さ
- 当院は東京都豊島区・東池袋エリアに位置し、東池袋駅直結とアクセス抜群です。副都心線・JR線の池袋駅からも徒歩圏内で、学校やお仕事帰りにも立ち寄りやすいロケーションにあります。人目を気にせずご来院いただけます。予約優先制で待ち時間も少なく、Webやお電話で当日予約も可能ですので、忙しい方もスムーズに受診できます。
梅毒は早期発見・早期治療が何より大切です。「もしかして…」と思ったら一人で悩まず、当院へお気軽にご相談ください。検査から治療、その後のフォローまで一貫して対応いたします。スタッフ一同、患者様の不安を和らげ安心して治療に専念できるよう努めております。しずく内科クリニック東池袋は、皆様の健康とプライバシーを守りながら、迅速・適切な医療サービスを提供いたします。
まずはお電話またはWeb予約にてお問い合わせください。梅毒に関する検査・診療のご予約は随時受け付けております。症状がある方も、症状はないけれどご心配な方も大歓迎です。私たちと一緒に早めの対策をとり、大切な健康を守りましょう。スタッフ一同、皆様のご来院を心よりお待ちしております。