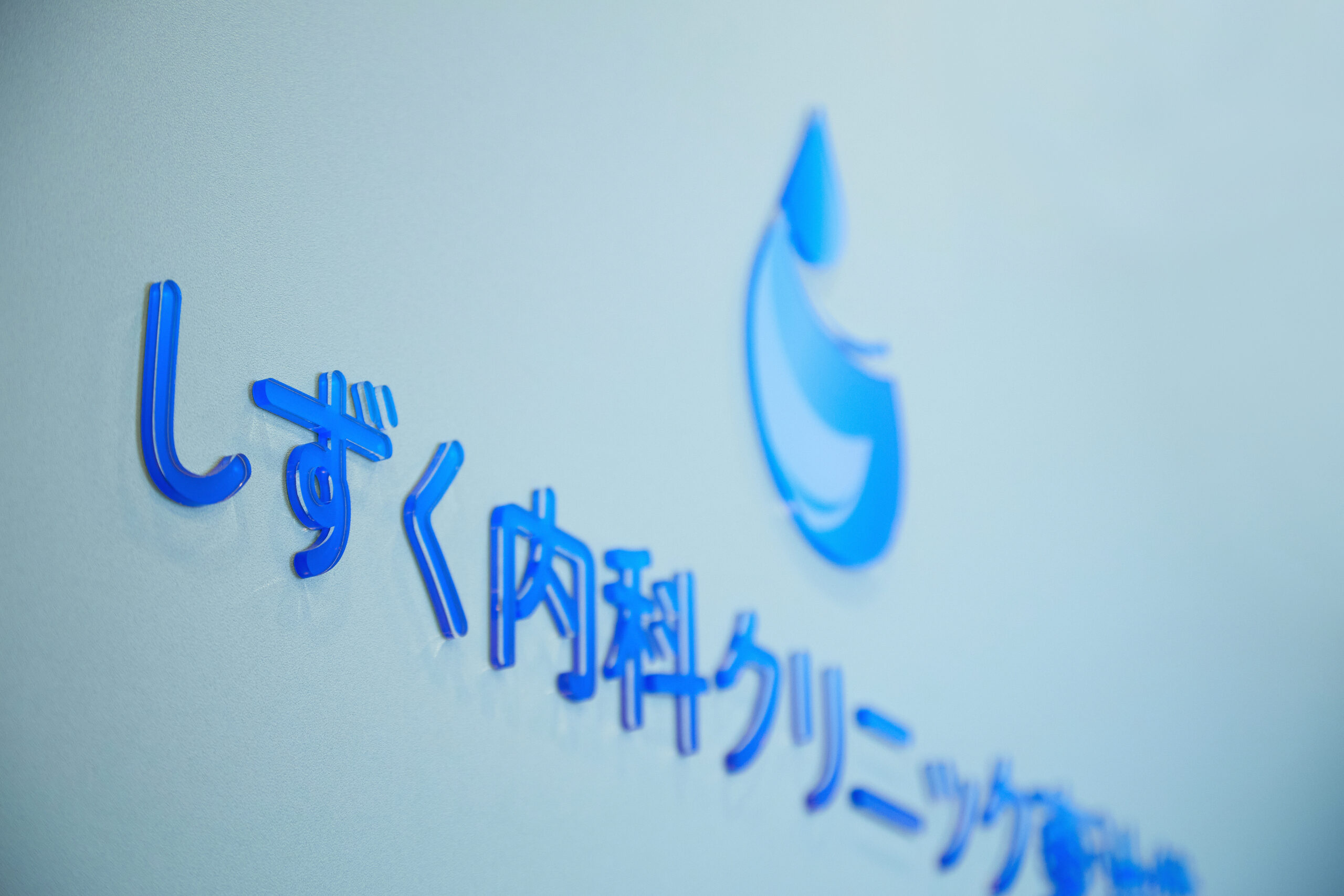百日咳とは
- 百日咳は、Bordetella pertussis(ボルデテラ・パータシス)という細菌が原因の急性呼吸器感染症。
- 主に咳が非常に長引き、場合によっては数カ月にわたって続く。
- 特有の咳音(吸気性笛声音)を伴い、特に乳児では重篤な症状となる場合がある。
百日咳は、気道の粘膜に感染して強い炎症を起こす細菌性疾患で、古くから「長く続く咳」の代名詞として知られています。とくに特徴的なのが「ヒュー」という吸気時の音を伴う咳発作で、これが数週間から長ければ100日以上続くこともあるため「百日咳」と呼ばれます。
世界保健機関(WHO)によると、百日咳は今でも世界中で年間約2,400万人が罹患し、16万人近くが死亡しているとされています。日本でも毎年数百件の報告があり、ワクチンの導入によって減少傾向にはあるものの、完全には根絶されていません。
症状と経過(カタル期・痙咳期・回復期)
- カタル期(1〜2週):微熱、鼻水、くしゃみなど風邪に似た症状。
- 痙咳期(2〜3週〜):突発的で連続的な激しい咳発作。
- 回復期(数週〜数カ月):咳の回数が減るが、再発しやすい。
百日咳の症状は、進行に伴い3つの時期に分かれて現れます。
まず「カタル期」では、発熱、咳、鼻水など、典型的な風邪と見分けがつかない軽度の症状が現れます。この時期は他人への感染力が最も強く、家庭や学校などで周囲にうつしてしまうことがあります。百日咳は「初期に診断しにくい」のが特徴で、誤って風邪として処理されてしまい、感染を広げてしまうことも少なくありません。
次の「痙咳期」では、強い咳が突発的に繰り返し起きるようになります。咳が連続して起きた後に、深く息を吸い込むため「ヒュー」という吸気音が出ることがあり、これが百日咳の典型症状です。特に乳児は咳が出せずに呼吸が止まり、チアノーゼ(顔色が青くなる)を起こすこともあるため、非常に危険です。
「回復期」になると咳の頻度は減りますが、完全に治るまでには長期間を要します。風邪や刺激によって再発することもあり、患者によっては3カ月以上続く場合もあります。
原因菌と感染経路
- 原因:百日咳菌(Bordetella pertussis)。
- 感染経路:主に飛沫感染(咳やくしゃみによる)、一部は接触感染。
百日咳菌は、細菌の一種であり、感染者の気道内に存在します。この菌は咳やくしゃみとともに空中に飛び散る微細な飛沫に含まれており、それを吸い込むことで感染します。いわゆる飛沫感染が主な感染経路です。
また、感染者が触れたドアノブや手すりなどを介して、間接的に菌が手に付着し、それを口や鼻に運んで感染することもあります(接触感染)。特に小さな子どもや乳児では免疫力が弱いため、家庭内に感染者がいると、重症化するリスクが非常に高くなります。
百日咳菌は、人にしか感染しないため、動物を媒介とすることはありませんが、その分、人から人への感染リスクは高いといえます。
治療法
- 主にマクロライド系抗菌薬(エリスロマイシン、クラリスロマイシンなど)を使用。ただし耐性菌増加のためST合剤も考慮。
- 発症初期(カタル期)に服薬開始すれば、症状と感染力を軽減可能。
治療には、細菌に有効な抗菌薬を使用します。百日咳菌に対して効果のある抗菌薬としては、マクロライド系(エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど)が第一選択です。
ただし、これらの薬剤が最も効果を発揮するのは「カタル期」と呼ばれる発症初期です。この時期に治療を開始すれば、咳の進行を抑えることができ、感染の拡大も防ぐことが可能です。逆に、痙咳期に入ってからでは抗菌薬の効果は限定的で、症状の自然経過をたどることになります。
近年ではマクロライド耐性菌の報告もあり、特に日本では2018年に初の耐性株が確認されました。2025年の流行ではこの耐性株が主流を占めていると報告されており、ST合剤(スルファメトキサゾール・トリメトプリム、バクタ他)を選択するなど今後は治療方針の見直しや耐性菌への警戒が求められます。
予防法(ワクチン接種)
- 主にDPT三種混合ワクチンやDPT-IPV四種混合ワクチン。
- 生後3カ月から定期接種が始まり、4回にわたって実施される。
百日咳に対しては、ワクチン接種が最も有効かつ現実的な予防法です。日本では、ジフテリア・百日咳・破傷風の三種混合(DPT)または、不活化ポリオを加えた四種混合(DPT-IPV)ワクチンが使用されており、定期予防接種として導入されています。
初回接種は生後3カ月から開始され、合計4回(3回+追加1回)に分けて行われます。接種率は高いものの、乳児が未接種のうちに感染すると重症化のリスクが非常に高いため、妊婦や保護者への追加接種も重要視されています。
また、海外では思春期・成人への追加接種を推奨する国もあり、日本でも今後議論が進む可能性があります。
疫学と流行状況
- 百日咳は3~5年周期で流行を繰り返す。
- 日本では、毎年おおよそ数百件~数千件の届出があり、乳幼児の重症化リスクが特に高い。
- ワクチン接種率や世代ごとの免疫保有率が流行に大きく影響。
百日咳は、流行の波が周期的に訪れる感染症として知られています。一般的には3年から5年に一度の頻度で、小規模な流行が発生します。日本では感染症法により、5類感染症として発生状況が常時監視されています。
たとえば、2020年には全国で約500件の届出がありましたが、過去には年間5,000件を超える報告があった年もあります。特に、ワクチンの追加接種(ブースター)を受けていない世代や、免疫が低下している高齢者が感染源になることも多く、乳児への家庭内感染が問題視されています。
世界的にも百日咳の患者数は減少傾向ではあるものの、低中所得国では依然として乳児死亡の原因のひとつであり、公衆衛生上の大きな課題とされています。
成人と乳児の症状の違い
- 成人やワクチン接種済み者では、軽い咳が数週間続く程度のことが多い。
- 一方で、乳児は重篤化しやすく、無呼吸やチアノーゼ、けいれんを伴うことも。
- 感染者本人が気づかずに乳児に感染させるケースが多い。
成人や年長児では、百日咳に感染しても症状が軽いため、風邪や慢性咳と勘違いされることがしばしばあります。特に、過去にワクチン接種を受けていても、年数が経過することで免疫が低下していくため、再感染が起こることがあります。
問題は、そのような軽症者が家庭内で乳児に感染させてしまうことです。乳児は免疫を持たない状態であることが多く、重症化しやすくなります。乳児の場合、咳の症状が目立たず、代わりに呼吸が止まる(無呼吸)や、顔色が紫になる(チアノーゼ)、さらにはけいれんや脳症を起こすこともあります。
したがって、乳児と接する可能性のある成人(特に両親、保育士、医療従事者など)は、百日咳への再感染リスクを意識し、予防や早期の受診が求められます。
診断方法(培養・PCR・血清検査)
- 鼻咽頭ぬぐい液の採取による培養検査が「確定診断」の標準。
- 発症初期はPCR法やLAMP法による遺伝子検出が有用。
- 抗体価(抗PT IgG)の測定も参考にされる。
百日咳の診断は、特に初期の段階では風邪との鑑別が難しいため、検査による確定診断が重要です。主な検査には以下のようなものがあります。
- 細菌培養検査:鼻咽頭ぬぐい液を採取し、百日咳菌の培養を行うことで確定診断が可能です。ただし、結果が出るまでに数日~1週間かかるため、急性期には使いにくいという課題があります。
- PCR・LAMP法:遺伝子検出技術を用いて百日咳菌の存在を迅速に確認できます。特に発症から2週間以内の検体で高い感度を発揮します。
- 血清学的検査(抗体検査):抗体(主に抗PT IgG)を測定することで、百日咳に感染していた可能性を把握することができます。主に感染後2週間以上経過してから有効です。
*当クリニックでは同時多項目PCR検査機器(BioFire® SpotFire®システム https://www.biomerieux-jp.net/biofire-spotfire/ )を導入しており検体採取後待ち時間20~30分ほどで百日咳菌、マイコプラズマ、新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスなど10種類以上の病原体を同時に検出することができます。
合併症と重症化リスク
- 乳児に多い合併症:肺炎、けいれん、無呼吸、脳症など。
- 成人でも肋骨骨折や尿失禁など、咳の激しさによる合併症が報告されている。
- 乳児では死亡例もあり、特に生後3カ月未満の感染が危険。
百日咳は、症状自体もつらいものですが、さらに注意しなければならないのは「合併症」です。特に乳児では以下のような重大な合併症が生じることがあります。
- 肺炎:細菌による二次感染で肺炎を起こすことがあります。これは死亡原因の1位とされています。
- けいれん・脳症:無呼吸や酸素不足によって脳にダメージが及び、後遺症を残すことも。
- 無呼吸発作:乳児では咳をうまく出せず、呼吸が一時的に止まってしまうことがあります。
一方で、成人でも「咳が強すぎること」による合併症が知られています。たとえば、肋骨の骨折、尿漏れ、不眠などが長期間続き、生活の質(QOL)が低下する例もあります。
感染予防対策(手洗い・消毒)
- アルコール消毒が有効。
- 咳エチケット、換気、手洗いが基本。
- 家庭内での感染予防は大人の行動がカギ。
百日咳は飛沫や接触によって感染するため、手指衛生と飛沫対策が非常に重要です。以下のような予防策が推奨されています。
- 手洗い・手指消毒:特に外出後、トイレの後、食事の前には必ず手を洗う。アルコールベースの消毒剤が有効です。
- 咳エチケット:咳やくしゃみをする際にはティッシュや腕で口を覆い、他人に飛沫を飛ばさないようにします。
- 換気:室内の空気を定期的に入れ替えることで、空気中の菌を減らすことができます。
- 家庭内対策:大人が軽症でも咳が続く場合はマスクを着用し、乳児に近づくのを控えることが重要です。
まとめ
- 百日咳は細菌性の呼吸器感染症で、長期間咳が続くのが特徴。
- 症状は3つの時期に分かれ、特に乳児では重篤化しやすい。
- 主な感染経路は飛沫感染。家庭内感染のリスクが高い。
- 早期の抗菌薬投与が効果的だが、耐性菌の問題も発生。
- 予防にはDPTまたはDPT-IPVワクチンが有効。
- 成人の軽症感染が乳児への感染源となることもある。
- 合併症として肺炎、脳症、無呼吸などがある。
- 診断にはPCRや抗体検査が利用される。
- 日常的な感染予防対策(手洗い・消毒)が重要。